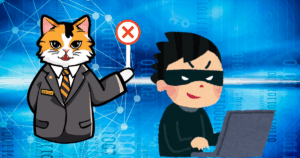「離婚しても、この家に住み続けたい」 そんな想いを抱える方は少なくありません。 特に、お子さんがいる家庭では「転校させたくない」「生活環境を変えたくない」といった理由から、家の問題は離婚の中でも大きなハードルになります。
ですが、住宅ローンの現実は、感情だけでは動きません。 今回は、離婚後の「住まい」の問題について、よくある誤解と実務上のポイントをお伝えします。
財産分与ってどうなってるの?
離婚時には、夫婦が結婚中に築いた財産を原則として公平に分ける「財産分与(民法768条1項)」という制度があります。
この制度の対象には、以下のようなものが含まれます。
- 預貯金
- 保険や投資資産
- 家具・車などの動産
- 自宅やマンションなどの不動産
- 住宅ローンなどの債務(借金)
ここで注意しなければならないのが、夫婦で婚姻中に取得した負債も分与の対象となることです。つまり、持ち家がある場合、たとえ夫名義のローンであっても、「ローン付き不動産」として、資産と負債のセットで精算対象になるのです。
たとえば:
- 住宅の市場価値が2,500万円
- 残っている住宅ローンが2,000万円 → 差額500万円が財産分与の対象
逆に、ローン残高が市場価値を上回るオーバーローンの場合は、残債が残り、分けるべきプラス財産がないと評価されることとなります。
名義とローンのズレが生む問題
また、実務上、以下のような状況はよくあります。
- 家の名義:夫
- ローンの契約者:夫
- 今後住み続けたい人:妻(子と同居予定)
このようなケースでは、妻が家に住み続けたいと希望しても、名義人・ローン契約者である夫が「売却したい」と主張すれば、法的には止められないリスクがあります。
「住み続けたい」と思ったら検討すべき選択肢
住み続けたい場合に、取り得る選択肢は主に次のようなものです:
- 住宅ローンを借換して、名義を自分に移す(再審査が必要)
- 財産分与の一環として、一定期間の使用を認める取り決めを行う
- 相手方が引き続きローンを支払い、使用に合意する(賃料設定や相殺)
注意点として:
- 使用貸借とすると、借地借家法の保護が受けられず、将来の退去リスクがあります。
- 「慰謝料と賃料を相殺する」などの文言を盛り込み、支払条件を文書化することで、トラブルを回避しやすくなります。
「とりあえず出ていく」は危険
感情的になって「もういい、出ていく」としてしまう人もいますが、無計画に家を出てしまうことで、住まいを確保できず経済的に苦しくなったり、生活環境が不安定になることがあります。
家の使用条件・ローン負担・名義の扱いなどについて、事前に取り決めて文書化しておくことが、後のトラブル防止に不可欠です。
【まとめ】
離婚して家に住み続けるには、感情論ではなく制度と仕組みを理解したうえで、交渉と準備を進めることが大切です。
住宅ローンや名義の問題は複雑で、素人判断ではかえって不利になることもあります。
家とローンの問題は、冷静な視点が不可欠です。 「後悔しない別れ方」を目指すなら、法律の専門家と一緒に整理していくことをおすすめします。
▶ 離婚と住まいの問題で悩んだときは、まずは、弁護士に相談してみませんか?
弁護士法人アストレイでは、コチラのページから、法律相談のご予約を承ってます。