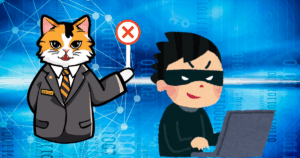ニャンゴシ君
ニャンゴシ君ねえ佐々木先生、よく『うちは財産が少ないから遺言なんていらないニャ』って言われるけど、どう思うニャ?



それ、実は一番危ない考え方ですね。財産の多寡にかかわらず、遺言がないことで揉めてしまうケースはたくさんありますよ。具体的に説明しましょう。



でもニャ、家族だったら話し合いでなんとかなるんじゃないニャ?



もちろん話し合いで解決するケースもありますが、相続人の数が多かったり、関係が疎遠だったりすると、感情的な対立になりがちです。特に不動産が絡むと厄介なんですよ。事例を見ながら説明しましょう。
【事例紹介】
たとえば、あるご家庭では、父親が他界したあとに残されたのは地方の一軒家とわずかな預貯金のみ。長男が10年以上同居し、介護も担っていましたが、遺言がなかったため、兄弟姉妹全員で遺産分割協議を行うことになりました。
ところが、疎遠だった弟が「自分の取り分も当然ある」と主張し、長男と激しく対立。家は共有状態となり、売ることも住み続けることも難しくなってしまいました。
遺言書があれば、こうした争いは避けられたかもしれません。



まさか、こんなに大変なことになるなんて…家族でも話し合いって難しいニャ



そうなんです。だからこそ、遺言で本人の意思を明確にしておくことがとても重要なんですよ。
【遺言があると何が違うのか?】
遺言とは、被相続人が“誰に何を相続させるか”を明確に意思表示する法的文書です。これがあることで、次のような違いが生まれます。
- 相続人の間で遺産の分け方を協議する必要がなくなる(遺産分割協議が不要になる)
- 一定の条件の下、相続人以外の第三者(たとえば内縁の配偶者や介護してくれた相続人以外の親族)にも遺贈できる
- 不動産の共有相続など、トラブルの種を事前に防げる
つまり、遺言は“争いの火種を消す消火器”のような存在なのです。
【遺言の民法上の効果】
遺言には、民法上明確に定められた法的効果があります。代表的なものとして、次のようなものが挙げられます。
- 相続分の指定(民法第902条1項)
- 遺産の分割方法の指定(民法第908条1項)
- 特定の財産を誰に与えるかの「特定遺贈」や、割合によって与える「包括遺贈」(民法第964条)
- 相続人の廃除やその取消し(民法第893条、894条)
- 遺言執行者の指定(民法第1006条)
これらは、遺言が法的に強力なツールであることを裏付けるものであり、被相続人の意思を確実に実現するための重要な制度といえます。
【遺言と遺産分割協議書の違い】
ここで混同されがちな「遺言」と「遺産分割協議書」の違いについても押さえておきましょう。
■ 遺言書
- 被相続人が生前に作成する意思表示文書
- 遺言に従って相続が進むため、原則として相続人同士で協議は不要
- 公正証書遺言であれば、検認も不要で法的効力が高い
■ 遺産分割協議書
- 相続人全員で“どう分けるか”を話し合って決めた内容をまとめた書面
- 相続人全員の同意(署名+実印+印鑑証明)が必要
- 一人でも反対すれば成立しない。調停・審判に進むこともある
つまり、遺言があれば協議そのものを回避できるケースが多く、トラブルの芽を摘むことができるのです。
【遺言を書くなら「健康寿命」も目安に】
「まだ元気だから、遺言なんて早い」――そう思っている方こそ、注意が必要です。
遺言は、書いた時点で「十分な判断能力(意思能力)」があることが前提です。認知症の診断を受けたあとや、判断力の低下が疑われる状況では、後になって遺言の有効性が争われるおそれもあります。
そこで参考になるのが、「健康寿命」という指標です。
厚生労働省によれば、日本人の平均寿命は男性約81歳、女性約87歳。一方、健康寿命(介護を受けず自立した生活ができる期間)は、それよりも平均して10年前後短いとされています。つまり、多くの人にとって、70代前半までが「元気なうちの遺言作成」の目安になるのです。
出典:厚生労働省『健康寿命の令和4年値について』
【まとめ】
遺言は、「万が一のときに備えるため」だけのものではありません。残された家族が、争いなく、円滑に、そして心穏やかにお別れできるようにするための、最後の思いやりです。
特に不動産がある方、内縁関係の方がいる方、家族関係が複雑な方などは、専門家に相談のうえ、早めの作成をおすすめします。
「うちは大丈夫」——そう思っている今こそ、行動に移すタイミングかもしれません。



なるほどニャ〜、遺言って“終活”というより“家族への思いやり”ニャ!



そうですね。ご家族の今後のためにという側面もありますので、終わりではなく未来への活動でもあるんですよね。
当事務所では、遺言作成をはじめ、遺産分割協議の調整、遺留分侵害額請求、さらには相続放棄や登記手続きなど、相続にまつわる幅広いご相談に対応しております。
ご本人のご事情やご家族の関係性に応じた、実情に即したアドバイスと文案作成を心がけており、『どこから手をつければいいかわからない』という段階でも、どうぞ安心してお話しいただければと思います。
ご相談をご希望の方は、コチラの【予約相談ページ】よりオンラインまたは対面でのご予約が可能です。