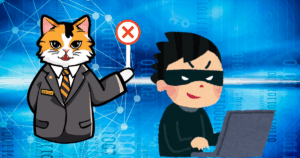ニャンゴシ君
ニャンゴシ君ねえ佐々木先生、親族が亡くなったあとって、何から手をつければいいニャ?



相続手続って、いざ自分が当事者になるとわからないことだらけですよね。今日は全体の流れをわかりやすく説明していきますね。



ありがたいニャ。でも、ちゃんと遺言がある場合とない場合で流れって変わるのかニャ?



その通りです。今回は“遺言がない場合”の遺産分割を前提にした説明になります。遺言があると、基本的にはその内容に従って進められますよ。
1.📜 相続のはじまりは「大切な人を見送ったそのあとに」
民法では、相続は死亡によって開始するとされており(民法882条)、財産を有する被相続人が亡くなると、その瞬間から「相続」が開始します。
相続が開始した場合、まずは、遺産分割の前提として相続人を確定する必要があります。
- まずやるべきは、戸籍を集めて“法定相続人”を確定すること(民法886条以下)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があり、時間がかかることも



戸籍って、本籍地が違うとあちこちに請求しなきゃいけないんだニャ〜
2.💰 財産の内容を調べるニャ
相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。遺産分割の前に、相続人がどのような権利義務を相続したのか確認する必要があります。
- プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券)だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査対象
- 通帳、残高証明書、登記事項証明書などを集めて「財産目録」を作成
- 相続放棄を考えるなら、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限なので要注意(民法915条1項)



最近はエクセルなどで財産目録を作る方も増えていますよ。



調査しきれなくて、後から被相続人の債権者に請求を受けるなんてこともあるから気を付けて調べるニャ!
3.📝 まずは話し合い(遺産分割協議)
遺言がなければ、まずは、相続人全員で、財産を「どのように分けるか」を協議します(民法907条1項)
- 原則として全員一致が必要。1人でも反対すれば協議は成立しません
- 話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印・印鑑証明を用意します
- 預金などは、銀行によって必要書類が変わりますので、事前に確認しておきましょう



話し合いって大事だけど、感情が絡むと難しくなることもあるニャ…



その通り。遺言があれば、その内容に従って分けるのが原則になりますがね。詳しくは『〈コラム〉遺言が“ある”と“ない”とでは雲泥の差』でも解説しているよ。
4.⚖️ 協議がダメなら、家庭裁判所ニャ!
相続人の一部が反対している、連絡がつかない、失踪しているなど、話し合いによって遺産分割を行うことが難しい場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることとなります。
ここで、気を付けなければならないのが管轄です。家事調停事件は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する」とされており、相続人の一人が遠方に住んでいる場合には、思わぬコストが発生することとなります(家事事件手続法245条1項)。
調停でもまとまらなければ、最終的には「審判」で裁判所が分け方を決めます
行方不明の相続人がおり、どうしても見つからない場合は「不在者財産管理人」を選任する手続が必要となる場合もあります。



遺産分割調停は、自分だけで進めるのが難しい場合もあるので、弁護士のサポートが有効ですよ。
5.🏠 不動産の名義変更は義務ニャ!
相続登記の義務化
遺産分割協議書を作成しても、それだけで安心している場合ではありません。2024年4月からは、相続登記が”義務化”されており、相続人は、相続した不動産の登記をしなければならなくなりました。
- 相続で取得した土地や建物は、名義変更(相続登記)が必要です
- 正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象に!
- 名義を変えないと売れない・貸せない・他の相続人との共有状態になるリスクも



でも先生、使わない山林とか、相続しても困る土地もあるニャ…



そんなときは『相続土地国庫帰属制度』という仕組みもあります。条件と審査がありますが、不要な土地を国に引き取ってもらうことができるんです。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です 。
- 法務局への申請 し、 審査に通れば国が土地を引き取る
- 対象外の土地(担保付き、建物あり等)には注意する必要がある
- 帰属を希望する土地1筆につき、14000円の審査手数料がかかる
- 原則として負担金20万円が必要



審査手数料や負担金も気になるところだけど、最近、利用者も増えてきているね。



固定資産税も馬鹿にできないニャ!
6.🧭 困ったときは専門家に相談するニャ
いかがだったでしょうか。遺産分割は法的・実務的に複雑な手続です。特に利害が対立する場合は、弁護士の関与が重要となり、登記や税務に関しては、司法書士、税理士といった他士業との連携が必要となることも少なくありません。
当事務所では、相続人の確定や財産調査、遺産分割協議書の作成はもちろん、調停や審判の対応、不動産の相続登記、さらには相続土地国庫帰属制度の活用についても、丁寧にご案内しております。
感情的な対立が避けられない場面や、相続人の間で意見がまとまらない場合でも、それぞれのご事情に応じた適切な対応策をご提案いたします。
ご相談をご希望の方は、コチラの【予約相談ページ】より、オンラインまたは対面でのご予約が可能です。



相続に関するご相談を幅広く承っています。調停や審判の対応も含め、お気軽にお問い合わせくださいね。



ニャンとも心強いニャ〜!早めの準備が一番の相続対策ニャ!


【執筆者プロフィール①】
弁護士 佐々木 良次(ささき・りょうじ)
弁護士法人アストレイ代表(東京・品川)
製造現場での派遣勤務を経て一念発起し、駒澤大学法学部、法科大学院を修了。司法試験合格後は、名古屋の企業法務系法律事務所にて契約・労務・紛争対応を中心に経験を積み、令和6年4月に東京・品川にて弁護士法人アストレイを設立。
現在は企業法務を基盤にしながらも、離婚・男女問題や遺産相続といった個人事件にも幅広く対応。特に、財産分与や婚姻費用の複雑な算定、親権・監護に関する紛争解決に力を入れている。
趣味はバイクとキャンプ。


【執筆者プロフィール②】
ニャンゴシ君
猫の社会的地位向上を夢見て、法曹界を志す。
以来、弁護士法人アストレイに“住み着き”、佐々木弁護士のそばで日々法律を学びながら、猫にも優しい社会の実現を目指している。
司法試験を受けたことはないが、「ボクの愛らしさはすでに合格レベルニャ」と本人(猫)は豪語。
趣味は、佐々木弁護士の家の壁紙での爪とぎと、冷蔵庫から勝手にちゅ〜るを取り出すこと。
最近のマイブームは、ネズミのおもちゃ