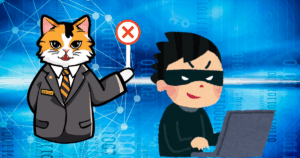ニャンゴシ君
ニャンゴシ君ねえ先生、離婚したら子どもってどっちが引き取ることになるのニャ?



基本的には夫婦で話し合って決めないといけないんだよ。子どものことを棚上げにして離婚を認めると、あとで大変なことになるからね。



ニャんと!じゃあケンカしてたら決まらないニャ!?



そういうときは裁判所が”子どもの幸せ”を一番に考えて決めてくれるんだよ。
1. 離婚時、子どもの親権はどう決める?(民法819条)
⑴ 親権とは
親権とは、子を監護教育するために父母に認められた権利義務のことを良い、父母が共同で行使することが原則です(民法818条2項)。
大きく、財産管理権と身上監護権に分けられ、その内容は、次のとおりです。
財産管理権
子ども名義の財産を、本人に代わって管理・処分する権利です(民法824条)。
また、子どもが何らかの法律行為をする際、それに“同意する権利”も含まれます。例えば、以下のような行為が該当します。
- 子ども名義の口座を作り、預貯金を管理する
- 子どもが相続した土地を処分する
- 子どもが携帯電話を契約するとき
- 一人暮らしのアパートを賃貸するときの同意
- 子どものパスポート申請を代理で行う
身上監護権
子どもと一緒に暮らし、食事や教育といった身の回りの世話を行う権利です(民法820条)。親は、身上監護権を行使するにあたっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとされています(民法821条)。
- 身上行為の代理権(民法775条、787条・804条):養子縁組や認知など、子どもの身分行為に同意・代理する権利
- 居所指定権(民法822条):子どもの住むところを指定する権利
- 職業許可権(民法823条):子どもの就職を許可する権利



親権の中身っていっぱいニャ!親って、色々大変ニャンだね!



お子さんを育てるっていうのは、それだけ大事なことなんだね。
⑵ 離婚の際は単独親権
民法819条1項は、協議により離婚する際に未成年の子がいる場合、父母のいずれかを親権者として定めなければならないと定めています。 現行法では、離婚後は必ずどちらか一方が親権を持つことになるのです。
(民法819条1項) 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で一方を親権者と定めなければならない。
裁判によって離婚するときや、協議で親権者が決まらなかった場合、家庭裁判所が親権者を決定します(民法819条2項、同条5項)。
2. 親権者指定は“子の利益”が判断基準
家庭裁判所では、「子の利益」を最も重視して親権者を判断します。
判断要素としては、次のような事情が考慮されます。
- 親の監護能力、家庭環境、居住・教育環境
- 子に対する愛情の度合い
- 従来の監護状況
- 実家の資産
- 親族の援助の可能性
- 子どもの年齢、性別、兄弟姉妹関係
- 子どもの従来の環境の適応状況、環境の変化への適応性
- 子どもの意向
- 父母および親族との結びつき
- 離婚に至る事情(虐待・DVの有無など)
実際には、特に子どもが幼い場合には、日常的に養育を担ってきた母親が親権者とされることが多く、実務上も母親が親権者となるケースが多数を占めています。
もっとも、養育実績や生活環境などによっては父親が親権者に指定されるケースもあります。



お金以上に問題になることもあるニャ?



もちろん!親としてはおざなりに出来ないからね。
面会や養育費のことなども含めて、子どもの将来のことに関わるから、しっかりと協議しないといけないしね。私もいつも気を遣うところだよ。
3. 親権と監護権は別?
親権という言葉とともに、「監護権」という言葉もよく耳にします。
「監護権」は、親権のうち身上監護権、つまり、子どもの心身の成長のための教育・養育を中心とする権利義務の総称のことをいいます。
離婚する場合および認知する場合には、監護権と親権とを切り離して、監護者と親権者を別個に定めることが可能です(民法766条1項、788条)
実際、離婚後に「親権は父」「監護権(実際の養育監督)は母」と分け、子どもの財産管理を父親が行い、日常の世話や教育は母親が担うというケースもあります。
ただし、トラブルの原因になることもあるため、慎重な設計と取り決めが必要です。



「親権」のうちの身上監護権が、よく言われる「監護権」って覚えとくニャ!
4. 「共同親権」が導入されるって本当?
現在の日本の法律では、離婚後の親権は「単独親権(どちらか一方のみ)」が原則です。
しかし、令和6年5月17日の民法改正により、令和8年5月までに「共同親権」の制度が導入されることとなっています。
これにより、父母双方が合意すれば、離婚後も共同で親権を持つことが可能になります。
「離婚しても一緒に子育てする」という発想が制度的に可能になることが大きな転換点ですが、DVや虐待の被害者が共同親権を不安に感じるケースも指摘されており、今後の運用が注目されます。
5.【まとめ】
離婚後の親権者指定は、名義のように「どちらかが欲しいと言えばもらえる」ものではなく、 子どもの利益を最優先に判断される事項です。
また、今後は「共同親権」が導入されることで、制度上の選択肢が広がります。
とはいえ、親権争いは当事者にとって非常にストレスがかかる手続きとなるため、 早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
▶ 当事務所では、離婚や財産分与、親権に関するご相談を多数取り扱っております。ご希望に応じて、オンライン(Zoom等)または対面でのご相談が可能です。詳しくは、プロフィール欄にある【離婚特設ページ】をご覧いただくか、相談予約フォームからご連絡ください。
🐱~ニャンゴシ君のひとこと~



親権って、名前に“権”ってつくくらいだから…なんか強そうニャ!



確かに大事ではあるけど、中身は“責任”と“義務”が詰まってるからね。



ボクは、これから、おやつの“権利”を主張していくニャ!中身の詰まったやつニャ!



ニャンゴシ君、そろそろダイエット考えようか。


【執筆者プロフィール】
弁護士 佐々木 良次(ささき・りょうじ)
弁護士法人アストレイ代表(東京・品川)
製造現場での派遣勤務を経て一念発起し、駒澤大学法学部、法科大学院を修了。司法試験合格後は、名古屋の企業法務系法律事務所にて契約・労務・紛争対応を中心に経験を積み、令和6年4月に東京・品川にて弁護士法人アストレイを設立。
現在は企業法務を基盤にしながらも、離婚・男女問題や遺産相続といった個人事件にも幅広く対応。特に、財産分与や婚姻費用の複雑な算定、親権・監護に関する紛争解決に力を入れている。
趣味はバイクとキャンプ。


【執筆者プロフィール②】
ニャンゴシ君
猫の社会的地位向上を夢見て、法曹界を志す。
以来、弁護士法人アストレイに“住み着き”、佐々木弁護士のそばで日々法律を学びながら、猫にも優しい社会の実現を目指している。
司法試験を受けたことはないが、「ボクの愛らしさはすでに合格レベルニャ」と本人(猫)は豪語。
趣味は、佐々木弁護士の家の壁紙での爪とぎと、冷蔵庫から勝手にちゅ〜るを取り出すこと。
最近のマイブームは、ネズミのおもちゃ