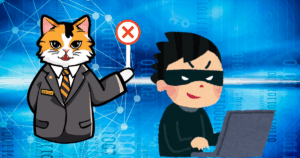「離婚調停って、裁判なんですか?」 「弁護士がいないと不利になりますか?」
そんな不安をよく聞きます。 実は、離婚調停は“話し合いの場”であり、裁判とは違う位置づけです。 今回は、離婚調停の基本的な流れや、臨む際の心構えについて解説します。
目次
【1 調停は「裁判」ではなく、第三者を交えた話し合い】
離婚調停とは、家庭裁判所で行う、第三者(調停委員)を交えた話し合いのことです。 夫婦二人きりでは冷静に話せない、あるいは話がまとまらないときに利用されます。
- 基本的に当事者は別々の控室
- 調停委員が双方の意見を交互に聞く形式
- 話し合いがまとまれば「調停成立」となり、法的な効力が生まれる
【2 離婚裁判を起こすには、まず調停から】
離婚を求めて裁判を起こすには、まず「調停」を経る必要があります。 これは「調停前置主義」と呼ばれ、家庭裁判所のルール(家事事件手続法257条)として定められています。
つまり、調停を飛ばして、いきなり裁判を起こすことはできません。
【3 調停の流れ】
調停は以下のように進みます:
- 申立書の提出(家庭裁判所に申立)
- 第1回調停期日の通知(通常は申立から1〜2か月後)
- 調停期日の実施(月1回程度のペース)
- 合意できれば調停成立/できなければ不成立
成立した内容は「調停調書」として記録され、基本的には確定判決と同じ効力を持ちます。
【4 弁護士は必要?】
弁護士の同行は必須ではありませんが、以下のようなケースでは強く推奨されます:
- 相手と直接やりとりするのが怖い・不安
- 相手が弁護士をつけている
- 財産分与や親権、養育費など法的な争点がある
弁護士がいれば、主張の整理や証拠の提出などもサポートしてくれます。
【5 調停で意識すべきポイント】
- 感情的にならないこと
- 希望条件を事前に整理しておくこと
- 第三者(調停委員)に対しても冷静に説明すること
また、調停が不成立になった場合、自動的に「離婚裁判」へと移行するわけではありません。 訴訟を希望する場合は、改めて裁判を提起する必要があります。
【まとめ】
離婚調停は、感情的な対立を整理し、合意形成を目指す“話し合いの制度”です。 事前に準備を整えて臨めば、冷静かつ納得できる解決に近づけます。
▶ 当事務所では、離婚や財産分与に関するご相談を多数取り扱っております。ご希望に応じて、オンライン(Zoom等)または対面でのご相談が可能です。詳しくは、コチラの【離婚特設ページ】をご覧いただくか、相談予約フォームからご連絡ください。