「社長が言ったから、来月から報酬は50万円で」
こうして役員報酬の金額が決まっている会社、意外と多いのではないでしょうか。
しかし、会社法上、役員報酬は社長や役員の裁量で勝手に決めてよいものではありません。定められた手続を踏まずに報酬を変更すると、税務上の不利益にとどまらず、会社への損害賠償責任や、刑事責任(特別背任罪)に問われるリスクすらあります。
本稿では、中小企業の経営者や実務担当者が最低限押さえておくべき、「役員報酬の決定・変更手続」について、法律と実務の観点から解説します。
1. 役員報酬は「株主総会」で決めるのが原則
会社法第361条1項は、取締役の報酬等について、次のように定めています。
「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益は、定款に定めがある場合を除き、株主総会の決議によって定めなければならない。」
つまり、定款に定めがある場合、又は株主総会の決議がない限り、取締役(代表取締役を含む)の報酬を支給・変更することはできません。
中小企業の中には、創業者や親族が株主を兼ねているケースも多いため、つい「社長のひと言で決まった」ような扱いをしてしまいがちですが、株主構成が相続などをきっかけに変動したり、長い間右腕として働いてきた役員に株式の一部を譲渡するなどしたことをきっかけに、これらの関係が崩れてしまうことがあります。
2. よくある誤りと、そのリスク
✅ ケース①:「定款を確認せず、なんとなく支給している」
定款に報酬額や決定手続が定められていない場合、必ず株主総会決議が必要です。報酬額を変更する際には改めて決議を取る必要があります。
✅ ケース②:「口頭で合意し、議事録もないまま支給」
議事録が残っていなければ、後に株主や相続人から争われた際、法的証明ができません。たとえ親族間の合意でも、形式を整えることが重要です。
✅ ケース③:「節税目的で報酬を途中から変更」
法人税の損金算入が認められるには、「定期同額給与」の要件(支給額・時期が一定)が必要です。期中の金額変更は、損金不算入となるおそれがあります。
3. 正しい変更手続の流れ
役員報酬を適正に変更するには、以下の流れを踏む必要があります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 定款を確認 |
| ② | 株主総会で報酬総額・対象者などを決議(定款に明記されていない場合) |
| ③ | 取締役会(ある場合)で個別額を決定 |
| ④ | 議事録を作成・保管(税務調査時にも必要) |
なお、定款、または、株主総会で「報酬枠(上限額)」を定め、具体的な支給額の決定は取締役会に委任することも可能です。
4. 無視した場合の「法的リスク」
【民事責任】
株主総会決議がないまま報酬を支給すると、取締役が会社に損害を与えたものとされ、損害賠償請求を受ける可能性があります。
【税務リスク】
「定期同額給与」に該当しない場合は、損金として認められず、法人税が増額されるほか、過少申告加算税の対象にもなり得ます。
【刑事責任】
さらに深刻なのが、会社法第960条1項3号の「特別背任罪」です。
取締役が、自己または第三者の利益を図る目的で任務に背き、会社に損害を与えた場合、
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその併科に処される可能性があります。
「社長が勝手に自分の報酬を引き上げていた」ことが、会社内部や株主に発覚し、告発されてしまう事例も実際に存在します。
5. 最後に:形式軽視が、最大のリスク
「うちは家族経営だから」「役員しかいない会社だから」――
こうした気の緩みが、将来のトラブルの火種になることがあります。
役員報酬の変更は、金額の多寡よりも、「正しい手続を経ているかどうか」が問われます。
株主総会の決議や議事録の保管といった基本を軽視せず、社内統治と法的リスク管理の両面から整備しておくことをおすすめします。




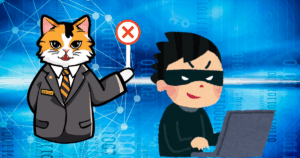
ニャンゴシ-取締役会-2-300x158.png)




