「株主総会は毎年なんとなくやっている」
「家族経営だから、議事録なんて特に作っていない」
そうした運営が日常になっている会社も多いのではないでしょうか。
しかし、株主総会の招集通知や議事録の手続を軽視したままでは、将来、決議自体の有効性を争われたり、登記・税務・訴訟などで深刻な不利益を被るおそれがあります。
本稿では、中小企業の経営者や実務担当者の方が押さえておくべき、以下2点について会社法に即してわかりやすく解説します。
- 株主総会の招集通知の基本ルール
- 議事録の作成義務と証拠としての機能
株主総会は「やらない」だけで違法となり得る
会社法296条1項により、株式会社は毎事業年度につき1回、定時株主総会を開催することが義務付けられています。
これは、たとえ非公開会社であっても同様です。
実際には、「取締役と株主が同じ人物だから」といった理由で形式的に済ませてしまったり、まったく開催していない会社も少なくありません。
しかし、そのまま決議も議事録も残していないと、決算承認や役員選任の効力が不確かになり、後に株主や相続人から「決議そのものが無効だった」と争われる事態にもなり得ます。
通知の期限は“2週間前”が原則、非公開会社は“1週間前”でOK
会社法第299条第1項により、株主総会を開催するには、原則として株主総会の日の2週間前までに、各株主に対して招集通知を発する必要があります。
ただし、同条ただし書および会社法300条により、非公開会社(譲渡制限会社)については、1週間前までに通知すれば足ります。さらに、取締役会設置会社でない場合は、定款によってさらに短縮することも可能です。
【例】7月15日に株主総会を開催する場合
→ 公開会社:7月1日までに通知が必要
→ 非公開会社:7月8日まででOK(定款で短縮可能)
通知の「方法」も重要、記録は命
招集通知の”方法”については、会社法299条第2項が重要です。
以下のいずれかに該当する場合には、通知は書面(紙)で行わなければならないと定められています。
- 株主が書面投票や電子投票を行うことができる旨を定めた場合(298条第1項第3号・第4号)
- 会社が取締役会設置会社である場合
また、299条第3項により、株主の承諾を得ていれば、電磁的方法(メール等)で通知することも可能ですが、 これはあくまで「書面通知の代替措置」であり、同意がなければメール通知は無効です。
◼️ 特に重要な実務上の留意点
株主間に対立の可能性がある場合や、親族株主との緊張状態があるような場面では、
内容証明郵便で通知を行うことが強く推奨されます。
通知内容や発送日時が公的に証明されるため、後に「通知されていない」と争われるリスクを最小限に抑えることができます。
また、たとえ株主が家族経営であっても、形式的に「通知する」ことが、外部からの監査や後継者対策の観点から重要です。もっとも、株主全員の同意が得られるようであれば書面決議も有効な選択肢の一つです(会社法319条)。
議事録がなければ、決議が「なかったこと」にされるおそれも
会社法318条により、株主総会では議事録の作成が義務付けられています。
議事録には、少なくとも以下の内容を記載する必要があります(会社法施行規則72条)。
- 株主総会が開催された日時・場所
- 株主総会議事録の経過要領・決議内容
- 会社法規定に定められた特定の意見・発言内容
- 株主総会に出席した各取締役の氏名・名称
- 株主総会に議長を立てた場合の氏名
- 議事録作成を行った取締役の氏名
この議事録は、株主総会の決議内容を証明する重要な書面資料となるため、作成・保存を怠ることは致命的です。
◼️ 実務での注意点
- 記載事項などを明確に記載しておく
- 少なくとも10年間は紙またはPDF等で保存
- 取締役変更や代表取締役選定を伴う場合は、登記と議事録の日付整合に注意
手続を軽視すると、すべてを覆されかねない
総会招集や議事録作成を軽んじてしまうと、
- 株主からの決議取消請求
- 株式譲渡時等の合意内容否定
- 相続時の代表権・役員地位争い
といった事態に発展し、会社の統治そのものが揺らぐことにもなりかねません。
特に中小企業や同族会社では「今は問題がなくても、将来問題が顕在化する」ケースが非常に多く見られます。
【まとめ】
株主総会は、会社の意思決定の“中枢”です。
形式をおろそかにしていると、後に「そもそも決議自体が違法」と主張され、全ての経営判断を覆されるリスクがあります。
- 株主総会は毎年開催する義務がある(296条)
- 招集通知は原則2週間前、非公開会社は1週間前(299条、300条)
- 取締役会設置会社では書面通知が必須(299条2項2号)
- 電子通知は株主の事前承諾を要する(299条3項)
- 議事録は作成義務があり、証拠の中核となる(318条)
いま一度、自社の株主総会の手続が正しく行われているか、点検してみてはいかがでしょうか。
【企業法務のご相談について】
当事務所では、企業の皆さまに対して、株主総会対応、契約書の作成・チェック、労務問題、債権回収など、幅広い法務サポートを行っております。
継続的なご相談をご希望の方には、顧問契約のご案内も可能です。
法務体制の整備や、気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。




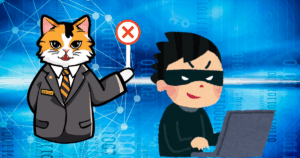
ニャンゴシ-取締役会-2-300x158.png)




