「突然、株主総会の招集通知が届いた」
「議題は“代表取締役の解任”。そんなバカな……」
中小企業や家族会社においても、「ある日突然、解任される」という出来事は、現実に起こり得ます。とくに、株主と経営陣が必ずしも同一でない企業では、株主の“数の力”によって、現経営者が追い出されるリスクが潜んでいます。
本稿では、代表取締役の「解任」を巡る法律構成や、知らないうちに進む“社長追放劇”の実態、そしてそれを防ぐための備えについて、会社法に基づいて解説します。
1. 株主構成がすべてを決める
株主総会の普通決議は、会社法309条1項に基づき、総会に出席した、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数で成立します。簡単に言うと、株式の過半数を持つ者が、取締役を選任・解任する権限を持つのです。
これは、代表取締役であっても例外ではありません。社長自身が経営していても、株式を持っていなければ「解任される側」に立たされる可能性があるのです。
✅ 典型例:
- 創業時に資金援助を受けた親族に過半数の株式を渡していた
- 元共同経営者が株式を持ったまま退任していた
- 株式譲渡により外部投資家が多数派になっていた
こうした“株主構成の歪み”が、静かに社長解任劇の引き金になることがあります。
2. 解任は「理由なし」で可能。ただしリスクも。
会社法339条1項の定めに基づけば、取締役の解任は、「いつでも」することができ、正当な理由は必要とされません。 つまり、「なんとなく気に入らない」「経営の方針が合わない」という理由でも、株主の過半数が同意すれば解任は成立する可能性があるのです。
同条2項により、正当な理由なく解任された取締役は、会社に対して損害賠償を請求することができるとされています。
とはいえ、実務上は「経営方針の違い」や「信頼関係の喪失」が理由として主張されることが多く、解任を要求する側もそれなりに準備はしてますので、賠償が認められるハードルは高いのが現実です。
3. 招集通知が届いたときには、もう手遅れ?
解任を議題とする株主総会は、正しく招集されていれば、有効に開催できます。
招集通知については、会社法299条1項に基づき、原則として株主総会の2週間前までに通知を発する必要があります(非公開会社は1週間前でも可)。 また、299条2項により、株主の書面・電磁的方法による議決権行使を認めている場合や、取締役会設置会社では、通知は書面で行わなければならないとされています。
内容証明郵便等で通知がなされていれば、「知らなかった」という主張も通りにくく、手続の瑕疵を理由に決議を覆すのは困難となります。
✅ こういったリスクも
- 招集通知に気づいたときには、すでに決議に必要な議決権が確保されている
- 通知や議事録などの手続が整っていれば、裁判で争うのは、困難
4. 予防策は「株式管理」と「定款整備」
社長解任のリスクに備えるためには、日頃から以下の点を点検しておくことが重要です:
- 自分自身または信頼できる者が過半数の株式を保有しているか
- 株式の譲渡制限が定款でしっかりと定められているか
- 取締役の任期や定数の規定が会社の実情に合っているか
- ゴールデンパラシュート(解任時の退職金条項)などを整備
特に「名義株」や「相続で分散した株式」などは、将来の紛争の火種になりやすいため、早めの対応が求められます。
【まとめ】
- 株主総会の決議は「株主の数の力」で決まる
- 解任は理由がなくても成立する(ただし損害賠償請求の余地はあり)
- 通知・議事録が形式的に整っていれば、争うのは困難
- 株式と定款を管理しておくことが最大の予防策
「うちは家族会社だから大丈夫」と油断していると、ある日突然“社長解任”が現実になるかもしれません。
【企業法務のご相談について】
当事務所では、企業の皆さまに対して、株主総会対応、定款整備、役員構成の見直し、事業承継対策など、幅広い法務サポートを行っております。
継続的なご相談をご希望の方には、顧問契約のご案内も可能です。
自社のガバナンス体制や株主構成に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
▶ご相談の予約はこちらのページから

執筆者プロフィール
弁護士 佐々木 良次(ささき・りょうじ)
弁護士法人アストレイ代表(東京・品川)
製造現場での派遣勤務を経て、一念発起し駒澤大学に進学。法科大学院を経て司法試験に合格。
名古屋の企業法務系法律事務所で中小企業の契約・紛争対応を経験したのち、令和6年4月に東京にて弁護士法人アストレイを設立。
現在は、企業の法務体制構築、株主総会運営、役員構成の見直し、契約書の整備など、会社の法務支援を幅広く手がけている。
趣味はバイクとキャンプ。




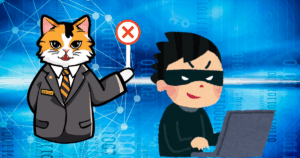
ニャンゴシ-取締役会-2-300x158.png)




